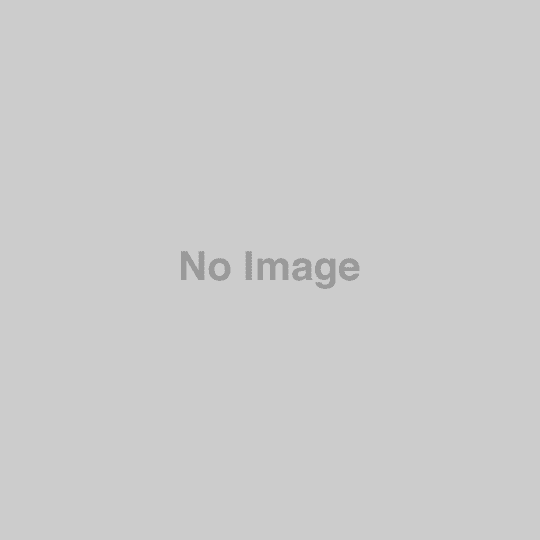[造手] TRINCHERO / トリンケーロ
[銘柄] Bianco / ビアンコ
[国] Italy / イタリア
[地域] Piemonte / ピエモンテ州, Asti / アスティ県, Agliano Terme / アリアーノ・テルメ
[品種] Arneis, Malvasia / アルネイズ, マルヴァジア
[タイプ] オレンジ / 辛口 / ミディアムボディ
[容量] 750ml
<輸入元テイスティングコメント:Edited by essentia>
マセレーションの期間は長くはないが、果皮成分は十分に抽出されており、しっかりした味わいと果実味。マセレーションをした白ワイン特有のたっぷりとした、濃密な香り。
<栽培:Edited by essentia>
標高250m。粘土石灰土壌。畑は南東向き。植樹:1982年。
<醸造:Edited by essentia>
ステンレスタンクで2週間マセレーション後、ステンレスタンクで1年間熟成。
<ストーリー:Edited by essentia>
【ワイナリーと造り手について】
アスティで代々長熟型の素晴らしいバルベーラ酒を造るトリンケーロは、ピエモンテを代表するリストランテ・ダ・グイードの経営者一族でもあります。ワイナリーは貴族が所有していた別荘地の一部で、歩いて数分のところに、19世紀前半にヴィスコンティ家オルナヴァッソ男爵によって建てられた古い農家と教会が今なお残っています。
1920年代にエツィオの祖父兄弟、セコンドとセラフィーノの所有となり、エツィオの父レナート、そしてエツィオへと受け継がれてきました。またトリンケーロはワイナリーとしては、1925年よりブドウおよびワインの生産を始め、アスティ県で最も早く、葡萄栽培農家による自家ビン詰めを行うための登記をした造り手(1952年)でもあります。
エツィオが初めてワイン造りに関わったと覚えているのは1978年、エツィオが14歳の頃。祖父と父と一緒に醸造だったそうです。1982年には本格的にワイン醸造を始め、父の時代までのようにバルベーラだけを生産するのではなく、醸造手法を変えたり、多くの品種を植えたりと、多くの実験を行ってきた。かつては50haを超える畑を有していましたが家族運営で理想とするワイン造りを実現するには、より小規模での生産が不可欠だと考え、ワイナリーに近い畑や、最上の区画を残し、他はワイナリーに販売し、現在は13haを耕作しています。
【畑と栽培について】
ワイナリー成立経緯もあり、トリンケーロの所有する13haの畑の多くにはバルベーラが植わっています。最も古い畑は「アスティの宝石」とマット・クレイマーも評す1925年に植えられた「ヴィーニャ・デル・ノーチェ」で、優れた土壌と日照に恵まれます。同じくバルベーラの古樹(1936年植樹)であるバルスリーナなど、バルベーラを主体に、10品種ほど栽培している。
バルベーラ以外の品種はエツィオがワイナリーの運営を任されてからの1980年代に植えられた。常に完熟を目指し、各品種のランゲとは違うはずの、アスティでの表現を常に考えてきました。その中には、品種としての市場の需要があまりにないため、生産を現在はあきらめたキュヴェもあります。例えばドルチェットは現在も栽培はしているが、ブドウは売ってしまっていますので、白品種への一部植え替えを2022年現在検討中だそうです。
【セラーと醸造について】
エツィオはワイナリーの運営を任された当初から、より“アスティ”らしいワインを造るということはどういうことかを考えてきました。そして、90年代後半に転機が訪れます。グラヴナーをはじめとする、フリウリの偉大な造り手たちのマセレーションの白ワインを飲んで、その飲み心地のよさに扉が開かれたような思いだったそうで、全ての白品種でマセレーションでの醸造を始め、そのうえで面白みに欠けたコルテーゼは、他の白品種に植え替えました。
白ワインだけでなく赤ワインも含め、それまでのワイン造りとは全く違ったワイン造りを模索し始めます。バリックの使用をやめ、新たに小型のボッテを買い、よりクラシックなスタイルへと戻ったわけです。そして伝統を追求するエツィオの新しい試みは実を結びます。ゆっくりと時間をかけて仕上げられるワインは、いずれも優雅な味わいで、ユニークな個性にあふれています。
【白ワインについて】
白品種はコルテーゼ、アルネイズ、シャルドネ、マルヴァジーアを1980年代に植えた。マルヴァジーアについては、マルヴァジーア・ディ・カンディア、マルヴァジーア・イストリアーナなど複数のクローンを植えた。マルヴァジーア・ディ・カンディアはエミリア・ロマーニャ州で主に栽培されるクローンで、食用ブドウとしてもアロマが強くておいしい品種。
ワインにするにはそこまで面白くないのでは、という意見が多く、エツィオ自身も“物は試しに”程度で植えてみただけだったが、出来上がったワインの中で一番エツィオが気に入ったのは、マルヴァジーア・ディ・カンディアだった。そのためマルヴァジーアは全てディ・カンディアのクローンへと接ぎ木、植え替えを行う。
ちなみに最初の1,2VTはアパッシメントを行い甘口を造っていて、そのスタイルを造り続けようとも思ったが、通常のスティルワインの方が生産本数も多く作れるし、楽しまれるシーンも多いと考え、甘口づくりはやめてスティルワインのみの生産へとシフトした。
そして90年代の終わりに転機が訪れる。グラヴナーをはじめとする、フリウリの偉大な造り手たちのマセレーションの白ワインを飲んで、その飲み心地のよさに扉が開かれたような思いだったそうだ。全ての白品種でマセレーションでの醸造を始め、そのうえで面白みに欠けたコルテーゼは、他の白品種に植え替えた。
2022年現在、シャルドネ(パルメ・ビアンコ)だけが樽発酵・樽熟成で、他はステンレスタンク醸造だが、ビアンコ(マルヴァジーア、アルネイズ、シャルドネのブレンド)も樽熟成を試そうかと考え中。シャルドネについては、2017年より全房発酵(破砕はする)を始めたが、鉱物感と垂直性が顕れとても満足している。
【202211 トリンケーロ来日】
◆ワインのバランスについて
ワインの酸には多くの種類があり、ワイン全体のバランスを考えるうえで、どれか一つの酸を取り上げてワインの品質を評価することは、不毛な議論を呼ぶことになる。特に揮発酸はやり玉に挙げられるが、ワインのバランスをとる上で非常に重要な要素。特に果実味の強い年は、高い揮発酸が不可欠と考える。
マセレーションをした白ワインにおけるタンニンについても、抗酸化物質であるからマセレーションをしている分、亜硫酸の添加量を減らせるということもあるが、タンニンがある種の“塩気”のように作用し、ワイン全体に引き締まりを与えるということも重要なポイント。
◆収穫のタイミングについて
新梢が出てこなくなり、一番上の葉の色が鮮やかな緑色から深い緑色になってきたら、ブドウの樹の一年のサイクルの終わりの合図。その他にもブドウに触った時の感触、ブドウの実の茎とのつながりの部分が赤茶色になってきているかどうか。さらにそのつながり目部分が乾いてくると完熟の合図だ。さらに待つとバルベーラの場合は、ブドウの皮が割れ始めるので急いで収穫しなければならない。ネッビオーロとフレイザは果皮が厚いので、ブドウの果皮が割れる心配はない。収穫のタイミングを決めるうえで、タネの成熟はもちろん大事だが、判断要素はそれだけではない。
マット・クレイマーのバルベーラ論
ピエモンテを愛し熟知するマット・クレイマーは、トリンケーロについて次のように絶賛しています。
単一畑が二カ所あり、ヴィーニャ・デル・ノーチェとバルスリーナである。ヴィーニャ・デル・ノーチェは多分、伝統的に作られる最も偉大なワインである。樹齢は非常に高く、最古のものは1929年にさかのぼる。バルスリーナも同じく樹齢が高くて1936年にまでさかのぼるが、オークの小樽で熟成される(現在はボッテに変わっている)。この二者は、それぞれ独自の流儀をいきながら、最上のバルベーラ・ダルバ酒と覇を競いあっている。
すべてのピエモンテ産ワインのなかで、なによりの好みはバルベーラ酒である。むろんのこと、バローロ/バルバレスコ/ガッティナーラといった、いずれもネッビオーロ種によるピエモンテの赤ワインはたしかに偉大である。けれども、私がもっとも頻繁に手を伸ばすのは、バルベーラ。ピエモンテに住む友だちは私の好みをおもしろがりはするが、べつに私に異議を唱えはしない。ただ、バルベーラの悪評があまりに長くイタリア国内を領しただけに、彼らに混じり住む一アメリカ人がバルベーラを「夢のようなデイリー・ワイン」と考えているのが、どうしても信じにくいのである。
念のためにいえば、この私だけがバルベーラ好きなわけではない。アルフレード・クッラード/ジュゼッペ・コッラ/アルド・コンテルノ/ジョヴァンニ・コンテルノ/エンリーコ・スカヴィーノ/アンジェロ・ガイヤ/エリオ・グラッソ/レナート・トリンケーロ(エツィオの父)や、そのほか数十人のピエモンテの栽培醸造家が、長いあいだ間尺に合わないほどバルベーラの古木を手入れしつづけている。それというのも、彼らがバルベーラの実力を信じているからのこと。
極上のバルベーラですら、つい最近までばかげた安値しかつかなかったから、これはともかく割に合わない仕事であった。多くの場合、彼らは同じ区画にネッビオーロを植え、(資格さえあれば)バローロやバルバレスコを名乗る有利なワインを造ることもできたのだから。
バルベーラの問題点は――というより、かくも悪評と低価格をもたらす原因は――その雑草さながらの生命力である。ネッビオーロとはちがい、バルベーラはどんな場所でも育つかのよう。おまけに、これまたネッビオーロとはちがい、造り手が当惑するくらい高収量なのである(かつて窮状にあえいでいたピエモンテの農民にとっては、困惑どころか、歓迎すべき性質だった)。
イタリアワインの権威バートン・アンダーソンの指摘によれば、ピエモンテといわずイタリア全土でワインはすべて男性形をとるのに(たとえば、il Nebbiolo、il Dolcetto、il Freisa)、バルベーラだけがla Barberaと女性名詞であるとか。言葉そのものに愛情が乗り移っている証である。
しかし、この愛情は品質にまで及ばなかった。バルベーラは農民のためのブドウと考えられ、高い収量と植える場所を選ばない安直さが、その魅力だった。
1800年代後半、ピエモンテはむろんのこと、ヨーロッパの全ブドウ畑を破滅に追い込んだフィロキセラ禍のあと、ワイン不足に陥った農民はバルベーラへと向かった。1900年代の初頭、バルベーラはいたるところに植えられ、ピエモンテのブドウ畑はかつて例のないほどバルベーラで溢れかえった。その帰結が、今日にまであとを引く、量産型の粗野なバルベーラ酒の大群であった。ピエモンテでバルベーラは、つまらぬ安ワインの代名詞になりさがった。
こうしたいきさつを知るだけに――たとえ自家用か友だちのためだけにせよ――通常はネッビオーロにこそ相応しい土壌と陽当たりの畑でいまだにバルベーラを植えつづける人々に、いっそう心を打たれる。また、そういう栽培家が収量を厳しく抑えるためにバルベーラをきつく剪定し、風味が凝縮されたひとしお濃密なワインを造ろうとしていることにも、やはり心を打たれる。
さて、そこにイタリアワインのルネサンスが到来した。バルベーラを信じ続けてきた造り手は、とうとうバルベーラへの献身が報われることになる。価格は劇的に動き、その実力に相応しいレベルにまで上昇した。バルベーラは、初めて尊敬を集めることとなった。
卓越した立地にある低収量の古木から造られた本物の優れたバルベーラ酒は、ほとんどバローロなみの熟成に耐えて上手に変身しうることに、イタリアワインの愛好家たちはようやく気づいた。
これらの再生を遂げたバルベーラのうちあるものは、醸造所の内部で従来とは異なる扱いをうけることにより、注目と尊敬に浴した。かつてすべてのバルベーラは、伝統的に木製の大樽をあてがわれた。ところが、フランス製の小樽(いわゆる「バリック」)で赤・白ワインを熟成させるという世界的流行が、80年代のピエモンテに押し寄せた。旧式の大樽の容量が3000−6000ガロンなのに対し、これら小ぶりなバリックには200Lほどしか収まらない。
単位あたりのワインが樽と接する表面積の割合が飛躍的に増すことは――とりわけ新樽あるいは2−3年しか使用されていない樽の場合――樽の中のワインにオーク特有のヴァニラ風味が溶け込むことを意味する。また、樽が付与するオークのタンニンは、ワインの味わいを滑らかにすると同時に、ワインの別の魅力である、より深くて濃い色合いをワインが保つのを助ける。フランスの森育ちのオークはとりわけ、興味深い繊細な風味をワインに与えるとされている。ちなみに樽の価格は1つ400から500ドルし、4−5年でその大切な風味が消えうせる。
高貴品種とはみなされてこなかったバルベーラに、かくも高価な樽と洗練された醸造技術を惜しみなく注ぎこむことは、昔気質のピエモンテ人にとって非常識なだけでなく、異端とも映った。実際、そこからもたらされた味わいのなかには、旧来のバルベーラと結びつくようなところが皆無である。けれども、それとは無縁なよそ者やモダン志向型のイタリア人は、ニュースタイルのバルベーラが気に入った。つまるところ、オーク仕上げされたワインは、彼ら好みのボルドー/ブルゴーニュ/高価なカリフォルニアワインなど、他の偉大な赤ワインを想いださせる。バルベーラは、尊敬すべきワインとなったのである。
“A Passion for Piedmont”「Italy’s most Glorious Regional Table」by Matt Kramer(1997年初版)より
(以上、輸入元ラシーヌの情報を基にエッセンティアにて編集。転載の場合は必ず引用元を明記のこと)
アスティ県で一番初めにDOCワインの自家元詰めを行うための登記をした造り手、トリンケーロ。現当主エツィオは3代目に当たります。当初から、自然環境に最大限配慮した農業を心がけ、セラーでも人為的関与を極力避け、納得できないものはボトリングしないワイン造り&大樽での長期熟成を理想としてきました。
元々は40haもの畑を所有していましたが、もっとも条件の良い畑13haほどを残して他はすべて売却もしくは賃貸しに。残した畑のなかでも、最も重要な2区画がワイナリーに隣接した畑ヴィーニャ デル ノーチェとその隣のバルスリーナ。ノーチェは1920年代に、バルスリーナは1930年代にバルベーラが植えられた畑です。粘土質で肥沃な地質を持つアスティ地区ということもあり、施肥をしなくてもアルコール度数の高い、凝縮した果実味を持つワインができると考える彼は一切の肥料を撒かず、ボルドー液以外の化学的な薬剤に頼らない農業を行っています。
バルベーラが主要品種ですが、その他にも9種類のブドウを栽培していて、白以外は全て単一品種でリリースさせていますので、ワイナリーの規模を考えると、非常に多種類のワインを造っていると言えます。
(以上、輸入元ヴィナイオータの情報を基にエッセンティアにて編集。転載の場合は必ず引用元を明記のこと)















![モッツァレッラ(グラスフェッドミルク)150g(100円アタリ税込767円)[毎週木曜入荷]](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/150892451_th.jpg?cmsp_timestamp=20240502151644)






![[購入条件付]ミニエール / アンフリュアンス(B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/188031933_th.jpg?cmsp_timestamp=20250828232736)





![[購入条件付]トリスタン・イエスト / ボー・ド・マルヌ (B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/187586615_th.jpg?cmsp_timestamp=20250801183734)