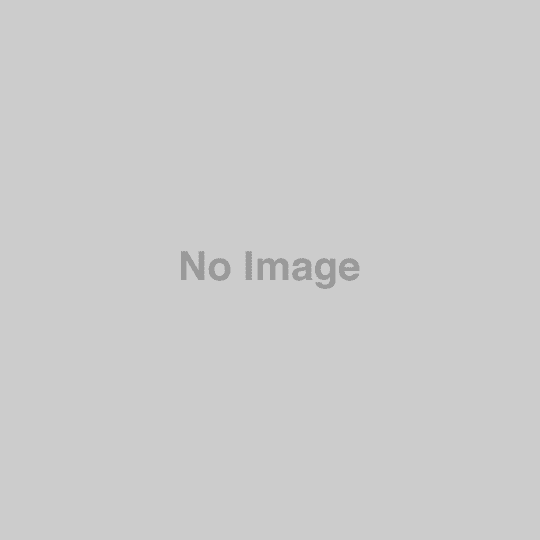[造手] L’Arco / ラルコ
[銘柄] Rosso del Veronese / ロッソ・デル・ヴェロネーゼ
[国] Italy / イタリア
[地域] Veneto / ヴェネト州
[品種] Corvina prevalente, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Teroldego / コルヴィーナ主体, ロンディネッラ, モリナーラ, サンジョヴェーゼ, テロルデゴ
[タイプ] 赤 / 辛口 / ミディアムボディ
[容量] 750ml
<銘柄エピソード:Edited by essentia>
気軽な食中酒を、と考えルーカが所有する畑の中でも樹齢の若いブドウを、ほとんどマセレーションをかけずにプレスをするので、明るいルビー色をしている。熟成には、セメントタンクと一部大樽が用いられ、フレッシュな果実味を損なわないように気を遣っている。サンジョヴェーゼやテロルデゴはほんの少量、遊び心程度に混醸されている。
<栽培:Edited by essentia>
位置:標高90−100m、土壌:粘土石灰質、植樹:1960年代−2000年代。その土地が必要としていることを尊重し、石灰、銅、硫黄、牛や馬の堆肥、など、天然物のみを使用しているが、ブドウの木が危険にさらされる可能性が例外的なケースでは、特定の製品を使用することを躊躇しない。
<醸造:Edited by essentia>
ステンレスタンクで数日間マセレーション、そのまま8ヶ月間熟成。その後、大樽とセメントタンクで18ヶ月間熟成。
<ストーリー:Edited by essentia>
【ワイナリーと造り手について】
ワイナリーの名前は、『ユピテルの拱門(きょうもん)』と呼ばれる石でできたアーチ(門)に由来する。この石造りの門の起源は16−17世紀にまでさかのぼり、ネグラール村を見下ろす(サン・ヴィート・ディ・ネグラールにある)丘陵に沿ってそびえるヴェローナ周辺にある7つの拱門のひとつである。ヴェローナからネグラールへ向かう道からも見え、数年前までフェドリーゴ一家はこの拱門の近くに住んでいた。醸造家ルーカ・フェドリーゴにとってこの拱門は、過去の記憶を呼び起こさせるものであり、その記憶こそルーカがワインの中に表現したいと願うものだ。
ルーカ・フェドリーゴの家は農家としてブドウと桃を栽培していた。
1996年、ルーカは14歳で両親からブドウ畑と桃園を引継いだ。その頃から、ルーカは、フェドリーゴ家がブドウ栽培農家としてブドウを供給していたジュゼッペ・クインタレッリ(Giuseppe Quintarelli)の元で働き始める。丁稚奉公のようなものだったのだろうか、ジュゼッペという職人の元で大きな経験を得、自身の家のブドウから1998年に初のアマローネを醸造した。
2000年には自身のセラーを両親のブドウ畑のすぐ隣に設立し、クインタレッリでの勤務と同時並行で、2001年から本格的に自社での生産、元詰めを開始。過去を尊重した積極的かつ礎のしっかりとしたワイナリーである。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統をそのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っている。バイオロジック栽培や、ナチュラルワインといったキーワードよりも、自他ともに伝統主義者と認めた師ジュゼッペ・クインタレッリに学んだ事を、忠実に実践している。
※ヴァルポリチェッラやアマローネの更なる理解のために、モンテ・ダッローラの生産者資料もぜひご覧ください。
http://racines.co.jp/rccms/wp-content/uploads/2014/12/Monte_dallOra_info202406.pdf
【畑と栽培について】
所有する7haの畑はネグラール村の周辺にある。その土地が必要としていることを尊重し、石灰、銅、硫黄、牛や馬の堆肥、など、天然物のみを使用しているが、ブドウの木が危険にさらされる可能性が例外的なケースでは、特定の製品を使用することを躊躇しない。
畑の面積は、自分の目の届く範囲にとどめており、数人の従業員とともに畑の管理を行う。畑の管理は分類するのならば慣行農法と言えるだろうが、師クインタレッリが行ってきたように、畑を庭のように管理する。
栽培品種はヴァルポリチェッラの土着品種だけでなく、サンジョヴェーゼ、テロルデゴ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニョン、なども少量栽培。DOC/Gのリパッソやアマローネだけでなく、ロッソ・デル・ヴェルネーゼやルベオなどの、土着品種もブレンドしたユニークなワインを生み出す。
【セラーと醸造について】
セラーはネグラールの村のはずれにあり、地下セラーは一年を通して一定の温度に保たれる。ヴァルポリチェッラという土地柄、フルッタイオ(陰干し部屋)が併設されているが、それ以外には特別な醸造設備の無いいたってシンプル。アパッシメント(陰干し)は風向きを計算された2階のフルッタイオで、細心の注意の元に行われ、自然の風も利用するが適宜、温度と湿度をコントロールの元行われる。
アパッシメントを行ったブドウで醸造した甘口ワイン。
ラルコのワイン
◆DOC取得
Valpolicella Ripasso Classico Superiore:ヴァルポリチェッラとアマローネのヴィナッチァ(搾り滓)を漬け込む。
Amarone Classico della Valpolicella:収穫後に乾燥させたブドウで造ったワイン。
Recioto della Valpolicella Classico:アパッシメントを行ったブドウで醸造した甘口ワイン。
◆IGT(DOCなし)
Rosso del Veronese IGT:収穫後すぐに圧搾またはほとんどマセレーションをしない。
Rubeo:アマローネとカベルネ・ソーヴィニョン(乾燥させたもの)のブレンド。(数年前の輸入元資料では、"カベルネ・ソーヴィニヨン"ではなく、"カベルネ・フラン(乾燥させたもの)"と記載されていた)
Pario:アマローネとヴァルポリチェッラ(リパッソではない)を各50%ブレンドしたワイン。
Pietrus:長期のアパッシメント(陰干し)を行い、アマローネの残糖値の上限を超えたワイン。
Passito Bianco:アパッシメントを行ったガルガーネガ主体の白の甘口ワイン。
以上の異なったコンセプトと個性を備えたユニークなワインを生産。ルーカの腕の見せ所だ。
『ラシーヌ便り』no.139 「生産者訪問記ラルコ」より(2017年6月)合田泰子筆
ラシーヌが紹介するイタリアワインの中で、もっとも人気の高いワインの一つ、ラルコ。2010年の初入荷から、早くも7年になります。ロッソ・デル・ヴェロネーゼ2012には、鮮やかな輪郭と、バランスよく活き活きとした味わいがあり、一段抜けた印象があります。ヴァルポリチェッラ・クラッシコ・スペリオーレ、パリオ、ルベオ、アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ、ピエトルスは、礎になるアマローネの質が向上したために、いずれも全体にレベルが高くなってきました。
「毎年、質の向上だけを考え、工夫している。2012と2015はともに暑くて、特に上級キュヴェはバランスがとりにくかった。が、どちらもわかりやすい美味しさがある。暑い年は葉を多く残し、成育中の傷んだブドウを取り除き、一房あたりの水分量を増やすように調節する。最近の年では2012が好きだ。2016は理想的な作柄だった。2007と2009はとても良いヴィンテージだ。2012と2015、2011と2016が似ているかな。2011、2016はバランスがとてもいい。2008と2010は収穫の途中に雨が降った。先に収穫したカベルネ・フランは良いけれど、リパッソとレチョートは難しい。9月中旬は季節の変わり目で、雨がちだから、難しいね。2013と2014は難しい年だったので、アマローネとレチョートを作れなかった。ロッソ・デル・ヴェロネーゼとヴァルポリチェッラはいい仕上がりになった。」
「グラッパは、トレンティーノのフランチェスキーニに蒸留してもらっている。彼らは羽のついた緑の帽子をかぶり、アルピネーゼと呼ばれる。フリウリとトレンティーノのような寒い地域に住む人たちにとってグラッパは欠かせないもので、昔から戦争に行く時グラッパを胸に入れて出かけた。だからグラッパづくりは、彼らの伝統なんだ。」
クインタレッリで学んだ基礎を忠実に積み上げ、自分の世界を作り始めた、と感じた訪問でした。
訪問後、ルーカからランチをご馳走になりました。ホワイトアスパラガスの前菜とカルチョーフィの古代米リゾットの、とても春らしいお料理とともに、ワインはもちろんクインタレッリ。ルーカから聞くジュゼッペ・クインタレッリの話は、いつも興味深い話ばかりです。
たとえばクインタレッリのラベルは、ジュゼッペの手書きではありません。「自分のサインなんて書きたくないから、代わりに書いて」と、ヴェローナでレストランを経営する友人のジョルジョ・ジョコに書いてもらったのが、かの手書きのラベルの始まりらしい。今は娘さんが書いたラベルが使われています。
1980年代半ば、突如クインタレッリの名前はアメリカでイタリアの最高峰として、評価され始めました。ニューヨーク・タイムズに「クインタレッリのワイン、ニューヨークに到着!」と書かれるほどでした。しかし、ジュゼッペ自身は、派手なことを好まない、冗談が好きな人でした。
モリナーラというワインを覚えている方もいると思います。1999年当時、前社ル・テロワールがビアンコ・ヴェロネーゼと共に輸入して大人気となった、クインタレッリのお手頃ワイン。このワインはモリナーラ種で作った、淡い色調の日常ワインでした。私たちも初めてこのワインを飲んだ時、「クインタレッリにこんなにチャーミングな親しみやすいワインがあるとは」と驚きました。とってもお手頃なワインが、クインタレッリの名前故、アメリカでは100ドルで売られていることを知り、ジュゼッペは作るのをやめてしまったそうです。なんと残念なこと。ワインに携わる者は、そのものの価値を誠実に消費者に届ける責任があると、あらためて感じたしだいでした。
ジュゼッペさんの晩年の十数年を、あたかも家族のように過ごし、その脇でつきっきりで学んだルーカのワインを、今ラシーヌが輸入しています。そのことをルーカから聞き知っていたジュゼッペさんは、きっとわがことのように喜んでくださったことと思っています。
(以上、輸入元情報を基にエッセンティアにて編集。転載の場合は必ず引用元を明記のこと)















![モッツァレッラ(グラスフェッドミルク)150g(100円アタリ税込767円)[毎週木曜入荷]](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/150892451_th.jpg?cmsp_timestamp=20240502151644)






![[購入条件付]ミニエール / アンフリュアンス(B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/188031933_th.jpg?cmsp_timestamp=20250828232736)





![[購入条件付]トリスタン・イエスト / ボー・ド・マルヌ (B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/187586615_th.jpg?cmsp_timestamp=20250801183734)