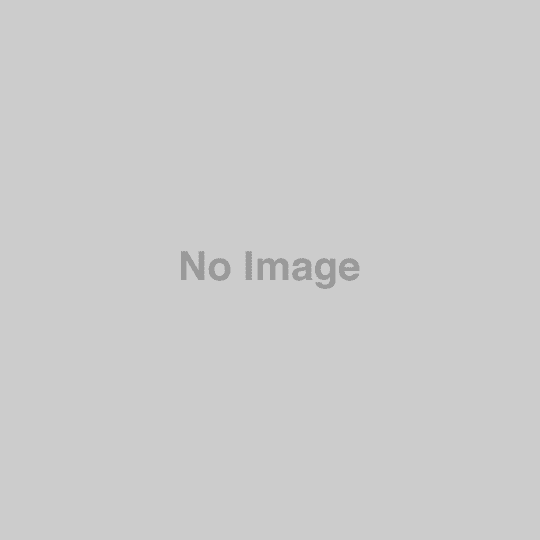[造手] Domaine Sylvain Pataille /ドメーヌ・シルヴァン・パタイユ
[銘柄] Marsannay Rouge Le Chapitre / マルサネ・ル・シャピトル
[国] France / フランス
[地域] Bourgogne / ブルゴーニュ, Marsannay / マルサネ
[品種] Pinot Noir / ピノ・ノワール
[タイプ] 赤 / 辛口 / ミディアムボディ
[容量] 750ml
<銘柄エピソード:Edited by essentia>
古くは聖堂参事会(教会支部=Chapitre)の所有していたとされる畑で、最初にブドウ樹を植えたのは大司教だとされる。5haの区画のうち、シルヴァンは北側斜面上部を所有。18世紀まではジュヴレと並び高く評価されていたとされるが、1936年に制定されたAOCの規格からはもれてしまったシュノーヴ村のクリマの一つ。砂砂利でカルシウムが豊富な土壌からは、優れたテクスチャーと骨格のワインが生まれるため、シルヴァンのワイナリーでの試飲でも最後に試飲されるワイン。この畑の重要性を長年訴えてきたシルヴァンだが、2019ヴィンテージからついにINAOがこの畑の格付けを地域名格から村名格へと変更した。
※果実味は減ってきますが、抜栓3週間経っても味わいは楽しめます。
<栽培:Edited by essentia>
標高300m、緩やかな斜面、土壌は泥灰土、石灰岩の小石、砂利でカルシウムが豊富。畑は東向き。植樹:1950〜1990年代。
<醸造:Edited by essentia>
木樽(新樽30〜35%)で15〜18ヶ月間熟成
<ストーリー:Edited by essentia>
【ワイナリーと造り手について】
シルヴァン・パタイユは、祖父の影響から幼少期からワインに対する情熱を抱き、その夢を実現するためにボーヌの専門学校で醸造を専攻。BTA(農業技術士資格)およびBTS(栽培・醸造の専門教育)をボルドーで醸造学を学びDNO(醸造学の国家資格)を取得し、専門的な知識を深めた。卒業後は分析所での勤務や醸造コンサルタントとして経験を積み、一時期はボーヌの醸造学校で教鞭をとる時期もあった。 1999年に祖父から1haの畑を引き継ぎワイナリーを興し、2001年9月には分析所を退職。2002年には9haまで管理畑を増やし、本格的に自身のワイン生産に注力し始めた(2010年頃までは畑の賃借や購入も2020年代に比べて格段に容易だった)。 現在(2025年)醸造コンサルタントとしての仕事先はコート・ドール全体で10件ほど続けており、ブルゴーニュ各地のその年ごとの畑や醸造の情報を知ることは、自身のドメーヌでの仕事の判断をすることにとても役立っているそうだ。ドメーヌは従業員15人体制で、20haの畑を管理、買いブドウ(ブルゴーニュ・アリゴテとブルゴーニュ・ルージュ)も含め毎年およそ10万本を生産している。
【畑と栽培について】
シルヴァンの管理する畑は20haの内、2.5haのアリゴテ、2.5haのシャルドネ、15haのピノ・ノワールの畑をそれぞれ所有または賃借している。これ以上、自社管理畑を増やすつもりはないが、アリゴテの古木がある畑であれば購入を検討する可能性はある。 ワイナリーの成長は生産本数だけでなく、品質面でも向上も同時並行で行い、バイオロジック農法(エコセール認証取得)は2007年に始め、バイオダイナミック農法も試験的に2008年から導入。すぐにブドウの品質の違いに気づき、全ての畑をバイオダイナミック農法(認証なし)へと転換した。
【セラーと醸造について】
セラーはマルサネ村に7つ所有しており、理想的には一つの大きなセラーに集約したいと考えている。しかし、そのような適切な土地はマルサネには存在しないため、現状のセラーを少しずつ拡張し、最終的には数を減らす計画を進めている(2025年)。 当初から自然酵母醗酵の重要性を認識していたが、2013年からは醸造時の亜硫酸の添加もやめた。2010年代はブルゴーニュ全体でも醸造時の亜硫酸無添加が広がった時期でもあるらしく、シルヴァンも味わいの変化に手ごたえを感じたそうだ。2013年は区画ごとに醸造していたアリゴテの区画ごとの瓶詰めを始めた年でもあり、多くの挑戦の年だったと振り返る。また亜硫酸無添加醸造を行うにあたって、畑の微生物環境を改善させることは絶対の必要条件であったともシルヴァンは語る。 シャルドネとアリゴテでは醸造はほとんど変わらず、垂直プレスで5,6時間かけて圧搾したブドウをデブルバージュせずにステンレスタンクに移し、醗酵が始まると樽へ移す。澱引きをすることはまれで、バトナージュも行わない。アリゴテはワインの特性上樽のニュアンスと合わないと考えているので、5年以上の樽を使い、新樽は主にシャルドネの醸造/熟成に使用される。 ピノ・ノワールは全房(50%-100%)で3-4週間のマセレーションを行い、全房比率は畑の樹齢や果実の成熟度による。樽での熟成は最低でも18か月、2年に及ぶことも普通で、醸造的介入を増やす代わりに時間をかけて醸造/熟成させることが果実の持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出すことにつながるとシルヴァンは考えている。 樽は400-500Lのトノーかトネルリー・ルソーの樽を好んで使用しており、白ワインでは20hlのフードルも一部使用。
【202502来日時】
マルサネはコート・ドール最北のワイン生産地ではあるが、ボーヌから30kmほどしか離れておらず、緯度による気候の違いはほとんどない。収穫時期に1週間ほどの差はあるが、マルサネのワインがコート・ド・ボーヌのワインより涼しさを感じさせることは、もはやない。それよりも、生産者の畑作業や区画ごとのミクロ・クリマのほうが、ワインの品質に決定的な違いを与える。 近年、気候は温暖化傾向にあり、特に水不足によるブドウの成熟停止が大きな問題となっている。この点で最も影響を与えるのが台木であり、南仏で使用される台木の導入も検討している。しかし、ブルゴーニュでは暑く乾燥する年が増えているとはいえ、ヴィンテージごとの気候差が大きく、収穫前の嵐も特徴的である。例えば、シャトーヌフ=デュ=パプでは毎年夏は暑く乾燥しており、それに適した台木を選ぶことは容易だが、ブルゴーニュではそうはいかない。実際、2021年と2024年は雨が多く、日照時間も非常に短かった。 雨が多く日照時間の短い年のワインは、軽やかで輝きがある(éclatant)。これはブドウの成熟をゆっくりと待つことができるためである。しかし、収穫をぎりぎりまで待つことは、腐敗果や獣害・鳥害による収量減のリスクも伴う。2024VTは日照時間の少ない年だったが、ボトリティスが付き始めるタイミングで収穫できたため、ワインの仕上がりが楽しみである。仕込みは昔ながらのブルゴーニュスタイルで、3週間以上の長いマセレーションとピジャージュをしっかりと行う。醸造中の管理には細心の注意を払うが、果皮の成熟を待って収穫できれば、熟成に耐えうる良いワインが生まれる。 暑く乾燥した年に収穫を待つということは、収穫前の一雨(嵐)を待つことを意味するが、近年はそれも期待できないことが多い。醸造面では、果皮の重たい成分を抽出しないよう、煎じるように穏やかに抽出すればよいため、それほど難しくはない。2018VTのように収穫前の雨がなかった年は、果皮成分の成熟が進まず、早く開くワインができる。一方、2015VTや2019VTのように暑い年でも、前年に雨が多かったり、適度な降雨があったりした年は、果実味も酸も力強く、長期熟成に適したワインが生まれる。ただし、それらのワインは2000年代以前のブルゴーニュのスタイルとは異なるものとなる。
改めて、収穫を待ち、果皮成分の成熟を見極めることの重要性を強調したい。2013年から全キュヴェで亜硫酸無添加醸造を開始したが、ポリフェノールは抗酸化物質であり、亜硫酸無添加の醸造においても重要な役割を果たす。
肥料については、秋冬の間に牛の堆肥を施している。本来は、秋前にハーブやマメ科植物の種を播き、春に緑肥として鋤き込むことが理想である。しかし、作業時期が従業員の夏季休暇や収穫期と重なるため、実現は難しい。過去3年間試験的に導入したが、作業日程の調整が困難で継続できなかった。
(以上、輸入元情報を基にエッセンティアにて編集。転載の場合は必ず引用元を明記のこと)















![モッツァレッラ(グラスフェッドミルク)150g(100円アタリ税込767円)[毎週木曜入荷]](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/150892451_th.jpg?cmsp_timestamp=20240502151644)






![[購入条件付]ミニエール / アンフリュアンス(B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/188031933_th.jpg?cmsp_timestamp=20250828232736)





![[購入条件付]トリスタン・イエスト / ボー・ド・マルヌ (B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/187586615_th.jpg?cmsp_timestamp=20250801183734)