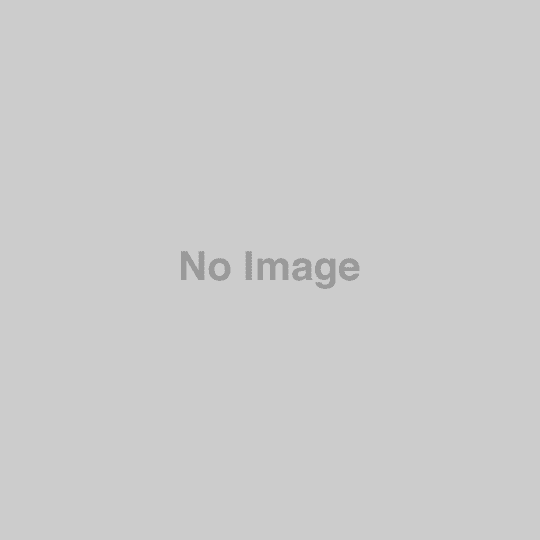[造手] La Castellada / ラ・カステッラーダ
[銘柄] VRH / ヴルフ
[国] Italy / イタリア
[地域] フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州 / Friuli Venezia Giulia
[品種] Chardonnay, Sauvignon / シャルドネ, ソーヴィニヨン
[タイプ] オレンジ / 辛口 / ミディアムボディ
[容量] 750ml
<栽培>
標高175m。ブドウ畑は全体で10ha。半分は樹齢45-55年、3000-3500本/haで、収量50q/ha。もう半分は樹齢25年ほどの新しいもので、5500-6000本/ha、収量は50q/haと少なめだが、その分熟成と凝縮度が高い。べと病とうどんこ病対策のため、硫酸銅と硫黄のみを使用。
<醸造>
樹齢50年の区画のシャルドネとソーヴィニョンを2ヶ月間マセレーションとアルコール醗酵。その後、大樽にて3年間、ステンレスタンクにて1年間の熟成。彼らのリゼルヴァ的位置づけの白。
<輸入元リリースノート>2024.12
フリウリのラ カステッラーダからは、2017ヴィンテージの白、高樹齢のシャルドネ&ソーヴィニョンで造るリゼルヴァ的存在のヴルフ2012、そして満を持してのリリースとなったユヅキ2009(詳細は後述します!)、そしてそして赤はメルロー2014とメルロー&カベルネで造るロッソ デッラ カステッラーダ2013をリリースします!
2015と2016ヴィンテージの完成度も素晴らしかったですが、リリース時点での表現力の豊かさという点では、2017は2年前の2015と1年前の2016を遥かに凌駕しているように思います。ビアンコとリボッラはもう少しだけ待っていただきたいですが、他の4つの白(ピノ グリージョ含む)はもうすでにサイコ〜!特にフリウラーノの味わいと香りの開き具合、その妖艶さには、皆さんゾッコン一目惚れとなること請け合いです。ビアンコとフリウラーノに関しては、ビックリするくらいの本数が届いていますので、ガンガンお使いいただけますと幸いです!
ヴルフ2012ですが、こちらもヤバいです!前回2016ヴィンテージの白が届いた際に、一緒にサンプルが届いていたので1年ほど定点観測をしてきたのですが、この1年がこのワインにとってどれだけ重要だったことか!30分くらい前に抜栓していただければ、全開バリバリです!2009に通じる、尊大なのに偉ぶらないワイン。
そしてユヅキ2009!自宅兼ワイナリーから歩いて1分とかからない場所にある、高樹齢のリボッラ、フリウラーノ、マルヴァジーアが混植するとて〜も小さな区画のブドウで造るワイン。もともとは近所の人が自家用ワインを造るために栽培していた棚仕立ての区画で、ワイナリー目線だと面積的にあまりにも小さく、品種ごとに収穫することが難しいため、3つの品種をいちどに収穫しなければならず、その結果としてブドウの熟度にムラが出てしまうので、これまではニーコの弟が経営する居酒屋用のワインに混ぜられていました。太陽に恵まれた2009年、すべてのブドウの熟度が揃った状態で成熟をしているのを確認したニーコ、単体で醸造することにするのですが、ちょうどその収穫の前後のタイミングでオータは生後8か月のユヅキを連れてカステッラーダを訪れます。ほっぺもふくふく、手首と足首には輪ゴムでもしてるんじゃないかってくらい全身ムチムチ&パッツパツなユヅキを見たニーコ、彼女の中に“太陽”ないし“陽”の雰囲気を見出し、彼女のためのワインは、この区画のワインにする事にしたそう…。圧倒的な情報量があるのですが、親しみやすく、ヴルフのような厳つさのないワインです。ニーコもオータも、2009年のカステッラーダの代表作はこのワインだと思っています!
赤2種は、カステッラーダが同時にリリースしてきたので、それ自体に意味があると考えまして、ヴィナイオータも一緒に売り出すことにしました。どちらもそれなりの年齢ですので、全然キャピキャピ(←死語?)はしていないのですが、2014はカワイイ系、2013はキレイ系とでも表現すれば良いのでしょうか。2014はフレッシュな果実と美しい酸に特徴のある裏表のない性格、2013は品もあり礼儀正しくもあるのですが、奥底に頑固さというか芯の強さのようなものを持った子な気がします。なんにせよ、美人姉妹であることは間違いないです!
造り手のストーリーはここをクリック
(以上、輸入元情報より引用)[]















![モッツァレッラ(グラスフェッドミルク)150g(100円アタリ税込767円)[毎週木曜入荷]](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/150892451_th.jpg?cmsp_timestamp=20240502151644)






![[購入条件付]ミニエール / アンフリュアンス(B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/188031933_th.jpg?cmsp_timestamp=20250828232736)





![[購入条件付]トリスタン・イエスト / ボー・ド・マルヌ (B20)](https://img07.shop-pro.jp/PA01409/288/product/187586615_th.jpg?cmsp_timestamp=20250801183734)